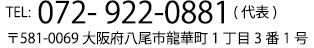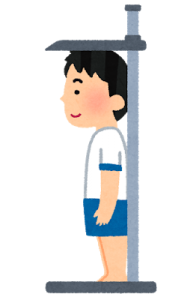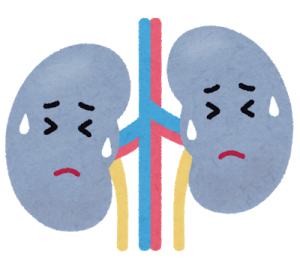診療科紹介
小児科
お知らせ
▶ アレルギー外来の診察について
アレルギー外来では一人一人の患者さんに十分な診察時間をお取りするため、原則予約制とさせていただいております。かかりつけ医から当院の地域医療連携センターを通して事前にご予約いただく形となります。
▶ アレルゲン免疫療法(ダニ・スギ花粉)について
ぜんそく発作がたびたび出現し、内服薬や吸入薬を長期にわたって使用しているお子さんはおられませんか。また、毎年花粉の飛散時期にひどいアレルギー症状が出てお困りのお子さんはおられませんか。当院では根本的に体質を改善する方法として、ダニやスギ花粉エキスを用いたアレルゲン免疫療法(皮下免疫療法および舌下免疫療法)を行っています。気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎でお悩みの方はぜひご相談ください。
アレルゲン免疫療法について詳しく知りたい方は
こちら をご覧ください。
▶ 食物経口負荷試験について
当院では食物アレルギーのお子さんを対象に食物経口負荷試験を行っています。現在、食事制限を行っているものの、いつから食事制限を解除して良いか悩まれている方はぜひご相談下さい。
▶ アトピー性皮膚炎について
赤ちゃんの湿疹が治りにくくアトピー性皮膚炎ではないかと心配されている方はおられませんか。外用薬(塗り薬)の使い方がわからず、お悩みの方はおられませんか。当院では正しい診断を行った上で、外用薬の塗り方などスキンケアについての具体的な指導を行っています。また、皮膚の状態が心配で離乳食の開始時期について悩まれている方には適切な食事指導を行っています。赤ちゃんに限らず、湿疹でお困りのお子さんがおられましたら、ぜひご相談下さい。
▶ 成長ホルモン分泌刺激試験(負荷試験)について
当院では低身長のお子さんを対象に成長ホルモン分泌刺激試験(負荷試験)を行なっています。詳細につきましては、各曜日の外来担当医にご相談いただければ、外来担当医が負荷試験の計画を立てます。背が低いことで悩んでおられる方はぜひご相談ください。
▶ 夜尿症(おねしょ)外来について
「小学生になってもおねしょが治らない」、「学校の宿泊行事までにおねしょを何とかしたい」、「おねしょで本人が自信をなくしている」など、おねしょで悩んでおられる方はおられませんか。
一般に夜間就寝中に目が覚めずにおしっこを漏らししてしまうことをおねしょ(夜尿)と言いますが、 5 歳以降のお子さんで夜尿が 1
か月に 1 回以上の頻度で 3
か月以上続くものは「夜尿症」と呼ばれ、治療の対象となる場合があります。夜尿症はお子さんやご家族にとって心理的な負担となることが多く、本人が自信を失い生活面に影響を及ぼすこともあります。「そのうち治るだろうと思っていたが、なかなか治らない」など、夜尿症でお悩みの方は一度お気軽にご相談ください。夜尿症外来では、はじめに十分な問診を行い、それに基づいて必要な検査や生活指導、薬物治療などを行います。
▶乳児血管腫(いちご状血管腫)に対する内服治療について
乳児血管腫はいちご状血管腫とも呼ばれ、赤ちゃんに比較的よく見られる赤あざの一種です。生後早期にあらわれ、急速に大きくなった後、5〜7歳までに徐々に小さくなります。これまで自然に小さくなるのを待つか、もしくはレーザー治療などが行われてきましたが、近年新たにプロプラノロールシロップによる内服治療が可能になりました。当院では副作用のないことを確認しながら投与量を決定しますので、初回導入時に1週間程度の入院が必要になります。乳児血管腫の治療でお悩みの方は遠慮なくご相談ください。
▶起立性調節障害に対する診療について
起立性調節障害は学童期に比較的多く見られる疾患で、起床困難、めまい、立ちくらみ、頭痛、腹痛、倦怠感などの症状が出現し、不登校につながることもあります。当院では主として問診や診察、検査による診断と治療を行っていますが、正確なサブタイプを判定する目的で入院による新起立試験を行うこともあります。
小児科について
当院の小児科では八尾市周辺地域の中核病院として、一般小児科診療のほか、地域住民の皆さんのニーズの高い小児救急および新生児医療に取り組んでいます。さらにスタッフの専門性を生かして、アレルギーや内分泌、神経、腎臓、膠原病、血液、夜尿症などの各専門外来を行なっています。また、当院は小児科専門医研修支援施設として専門医を志す若手医師の育成にも力を入れています。
スタッフ
| 補職名等 | 医師名 | 専門分野 | 学会認定など |
|---|---|---|---|
| 副院長 兼診療局長 兼医療安全管理室長 |
箕輪 秀樹 | 小児科、新生児、神経発達症 | 小児科専門医・指導医 新生児専門医・指導医 |
| 新生児科科長 | 道之前 八重 | 小児科、新生児 | 小児科専門医、 新生児専門医・指導医 |
| 小児科主任科長 | 井崎 和史 | 小児科、神経、新生児 | 小児科専門医 |
| 小児科科長 | 濱田 匡章 | 小児科、アレルギー、 膠原病、腎臓 |
小児科専門医・指導医、アレルギー専門医・指導医(小児科) |
| 小児科医長 | 吉川 侑子 | 小児科、内分泌 | 小児科専門医 |
| 小児科副医長 | 佐々木 彩 | 小児科、アレルギー | 小児科専門医 |
| 小児科副医長 | 久保 昂司 | 小児科、腎臓 | - |
| 小児科副医長 | 杉村 憲市 | - | - |
| 小児科副医長 | 南部 優志 | - | - |
| 小児科医師 | 平尾 桜子 | 小児科 | - |
診療体制
| 外 来 診 療 |
一般外来 (午前中) |
0歳から中学3年生までのお子さんが対象で、小児外科を除くすべての分野の疾患に対応しています。再診の患者さんのほか、地域の診療所・病院からの紹介患者さんの診察を行っています。 |
|---|---|---|
| 専門外来 (午後予約制) |
月曜日:アレルギー・膠原病外来、腎臓・夜尿症外来、内分泌外来 火曜日:アレルギー・膠原病外来、腎臓外来 1か月健診、免疫療法外来 水曜日:神経外来、予防接種 木曜日:食物アレルギー外来、乳児血管腫外来、NICU健診 金曜日:神経外来
|
|
救急外来 (輪番制) |
夜間・休日の小児一次救急は中河内地区の病院間で輪番制をとっています。当院の担当は毎週火曜日と土曜日で、診療受付時間は午前9時から翌朝8時までです。ただし、火・土曜日が祝祭日にあたる場合は午後7時から翌朝8時までとなります。)主に一次および二次の救急診療を行っています。 | |
| 入 院 診 療 |
小児病棟 |
肺炎や胃腸炎などの急性疾患のほか、アレルギーや膠原病、腎臓、血液、内分泌などの慢性疾患の治療を行なっています。また、食物経口負荷試験や成長ホルモン分泌刺激試験、排尿時膀胱造影、新起立試験などの各種検査入院にも対応しています。 |
| 新生児集中治療部 (NICU) |
当院は大阪府地域周産期母子医療センターに認定されています。主として低出生体重児や呼吸窮迫症候群、新生児仮死、胎便吸引症候群などの赤ちゃんに対して、24時間体制で呼吸・循環管理などの集中治療を行なって います。 |
|
| 院内学級 | 小児病棟には長期入院を要する学童患者さんのために市教育委員会による院内学級が設置されています。近隣の学校から専属の先生に来ていただき、直接指導していただくことで、学校での勉強を継続することができます。 |
専門外来のご案内
表1.負荷試験実施状況
(2020年1月1日〜12月31日)
| 食 品 | 負荷試験実施数 | 陽性症状(※) 出現例 |
アドレナリン使用例 |
|---|---|---|---|
| 卵 | 92件 | 16件(17.4%) | 0件(0.0%) |
| 牛乳 | 35件 | 11件(31.4%) | 0件(0.0%) |
| 小麦 | 38件 | 14件(36.8%) | 0件(0.0%) |
| その他 (大豆、そば、ナッツ類、甲殻類など) |
55件 | 17件(30.9%) | 0件(0.0%) |
| 計 | 220件 | 58件(26.4%) | 0件(0.0%) |
※陽性症状:発疹、喘鳴、腹痛、嘔吐、下痢、傾眠傾向など
■負荷試験の実施状況
2020年に実施した220件の負荷試験のうち、卵が42%、小麦が17%、牛乳が16%、その他(大豆、そば、ナッツ類、甲殻類など)が25%を占めており、陽性症状は220件中58件(26.4%)に出現しました(表1)。これまで何となく食事制限を続けてこられたお子さんの中には負荷試験で症状の出ない方も少なくありません。負荷試験の実施件数は以前に比べ減少傾向にありますが、当院では生後早期からのスキンケアに加え離乳食の適切な指導に力を入れており、その結果食事制限を必要としないお子さんが増えているものと思われます。
■負荷試験における陽性症状出現時の対応
2015年の負荷試験では、388件中154件(39.6%)に何らかの陽性症状が出現し、そのうちアドレナリンを使用したケースは6件(1.5%)ありました。しかし、2019年から負荷試験時の食物負荷量を調整したことで、アドレナリン投与を必要とするケースが2019年は1件(0.4%)、2020年は0件(0.0%)に減少しました。ただし、負荷試験には一定のリスクがあり、症状によってはアドレナリンを使用しなければならない場合があるため、当院では原則日帰り入院での負荷試験を行っています。
■加工品を用いた卵・牛乳に対する負荷試験
元来、乳製品の負荷試験は陽性症状の出現率が高く、どこまで摂取できるかを決めにくいケースが少なくありませんでした。当院では2014年から乳負荷試験に加工品(牛乳を含むホットケーキなど)を使用したことで、比較的安全に閾値(いきち)を決めることができるようになりました。同様に、これまで全く卵を食べていないお子さんに、卵を含むホットケーキから負荷試験を開始し、安全で良好な結果を得ています。このように卵、乳ともに加工品を継続摂取することで制限解除につながるお子さんが数多くおられます。
■消化管アレルギーに対する負荷試験

新生児・乳児消化管アレルギーでは人工乳を摂取した際に嘔吐や血便などの消化器症状を呈することが知られていますが、近年、人工乳に加えて固形物(卵黄、小麦、大豆など)でも同様の症状をきたすお子さんが増えています。これらのお子さんでは、通常の血液検査では診断が難しく、負荷試験を行うことが必要になります。当院では、人工乳だけでなく固形物による消化管アレルギーの診断・治療も行っています。
■花粉−食物アレルギー症候群

花粉-食物アレルギー症候群では、花粉抗原に対する感作が契機となって食物アレルギーを発症します。生の果物や野菜を摂取した際に口腔症状(口や喉のイガイガ感、唇のかゆみや腫れなど)を呈することが多く、全身症状(じんま疹や咳、腹痛など)を伴うこともあります。さらに、口腔症状を呈する食品が徐々に増加することもあります。中でも、大豆食品(豆腐、豆乳、大豆加工品など)を摂取することができなくなった就学児では、学校給食を食べることができず、学校生活に支障をきたすことがあります。
当院では、2016年から大豆を摂取できなくなったお子さん15人に対して、Birch-Mixという花粉エキス(国内では保険適用外)による アレルゲン免疫療法
を行ってきました。治療開始後早期から大豆食品を食べることができるようになるなど治療効果は良好です。導入時には入院を必要としますが、日常生活に困っておられる方は是非ご相談ください。
*アレルギー外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(2)神経(水・金曜日) 担当:井崎和史医師

【主な対象疾患】てんかん、熱性けいれんなどの神経疾患
けいれんを起こしたお子さんには、症状に応じて脳波や頭部MRI、SPECTなどの検査を行っています。そして、正確な診断および適切な治療を行うとともに、お子さんのQOL(生活の質)を維持できるよう家庭や学校での生活の指導を行っています。また、発達に遅れのあるお子さんに対しては、地域の施設と連携を取り早期療育や訓練などを行っています。
*神経外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(3)内分泌(火・金曜日) 担当:吉川侑子医師
*内分泌外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(4)膠原病(こうげんびょう)(月・火曜日)
担当:濱田匡章医師

【主な対象疾患】若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデス、若年性皮膚筋炎など
小児の膠原病自体、数は少ないですが、原因不明の発熱や手足の痛みが続くお子さんでは鑑別が必要になります。これまで膠原病の多くは難治性で治療法も限られてきましたが、近年、新たに生物学的製剤や免疫抑制剤を使った治療法が導入され、予後が大きく改善されてきています。当院では、これら最新の知見を踏まえた治療を行なっています。
*膠原病外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(5)腎臓 (月・火・木曜日)
担当:濱田匡章医師、久保昂司医師
*腎臓外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(6)夜尿症 担当:久保昂司医師

【主な対象疾患】夜尿症、昼間尿失禁(遺尿症)
5歳以降のお子さんを対象に、排尿記録の確認とともに尿検査や血液検査、腎尿路や脊椎の画像検査を行い、夜尿の原因となる基礎疾患がないかを調べます。その上で生活指導を行い、改善が見られないお子さんには行動療法(夜尿アラーム療法)や薬物療法(抗利尿ホルモン剤や抗コリン剤)を行います。
* 夜尿(おねしょ)外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(7)乳児血管腫

【対象疾患】乳児血管腫(いちご状血管腫)
赤いあざとして理解されている乳児血管腫は、自然に薄くなることや縮小することが多いことから治療をされないことも多いですが、目立つ場所にあって外見上気になる、盛り上がりの程度が強く自然に改善することが難しい、場所が拡大していく、といった場合に薬物治療を行います。
*乳児血管腫外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。
(8)循環器

【主な対象疾患】先天性心疾患、不整脈など
お子さんの生まれつきの心臓の異常や学校検診などで指摘された不整脈を胸部レントゲン検査や心エコー、心電図などを用いて詳しく調べます。検査結果によって治療方針や日常生活の管理方針が決まりますが、手術やカテーテル治療が必要なお子さんは専門施設を紹介しています。
*循環器外来についてのよくあるお問い合わせは こちら をご覧ください。